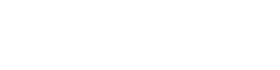噴火対策その2 防災用品、備蓄品
具体的な噴火対策を取り上げていきます。
火山灰から身体を守る対策
火山灰は「灰」と書きますが、実際はマグマが細かく砕けた「ガラス片」です。そのため、火山灰を吸い込むと喉を傷つけ、気管支炎を起こす可能性があり、危険です。目に入ると網膜を傷つける恐れもあります。また、火山灰には火山ガスが付着しているため、安全面・衛生面からも、できるだけ身体につかないことが望ましいです。
噴火が長期に渡る場合は、火山灰も長期にわたり降り続ける可能性があります(1707年宝永噴火は1ヶ月、1990年雲仙普賢岳噴火は途中小康を挟みつつ4年半)。最低でも3日間、できれば2週間以上の備えを考慮しましょう。
鼻・口・喉を守る:防じんマスク
火山灰が鼻や口から入ると喉を傷つけ、呼吸器障害を起こす可能性があります。1707年の宝永大噴火の際には、火山灰で呼吸器を患い、咳をする人が多数出たと記録されています。
降灰時に外出する際は必ず防じんマスクを使用しましょう。
通常のサージカルマスクでは横から火山灰が入り込む恐れがあるため、高機能防じんマスクが望ましいです。
目を守る:防じんゴーグル
火山灰が目に入ると網膜を傷つける恐れがあります。1707年の宝永大噴火の際には目の痛みを訴える人が増えたことが記録されています。外出の際は必ず防じんゴーグルをつけましょう。コンタクトレンズは外して下さい。
防じんゴーグルを選ぶ際の注意点は、できるだけ穴が空いていないものを選ぶことです。ゴーグルは曇りを防ぐために通気孔がついていますが、そこから火山灰が入り込む恐れもあります。穴が無いものか、下部についているものを選びましょう。また、眼鏡と一緒に装着できるゴーグルがお勧めです。
身体や衣服を守る:レインコート、ポンチョ、防護服など
火山灰は小さなガラス片である他、火山ガスが付着しているため、安全面・衛生面からも、できるだけ身体につかないことが望ましいです。外出時に衣服に火山灰が着くと、外出先や帰宅時に火山灰を室内に持ち込むことになります。全身を覆うレインコートやポンチョで全身を保護すると効果的です。
大量の火山灰が積もる地域で救援活動や清掃を行う場合は、全身防護服がお勧めです。
頭を守る対策:防災ヘルメット
火山の周辺では噴石落下の恐れがあるため、ヘルメットが必須になります。特に登山時は、マスク・ゴーグル以上にヘルメットが大事です。
噴石落下の恐れがない地域でも頭部の保護は重要です。火山灰が大量に降ることによって、思いもよらなかった建物や設置物の崩落が起こり得るからです。火山灰が積もった電線に雨が降ると、切断される可能性も予想されています。
また、火山灰そのものも、頭部に降りかかることは好ましくありません。室内に火山灰を持ち込むことになるうえ、風呂場で洗い落としてもつまりの原因になるためです。
頭部の保護は防災の基本となりますので、必ず1人1つ、防災ヘルメットを用意しましょう。
ヘルメットには転倒用と落下物用、またはその兼用があります。自転車用ヘルメットは転倒用の構造となっているため、防災用としては推奨されていません。防災用のヘルメットは落下物用を選びましょう。
火山ガスから守る:火山ガス用マスク
火山ガスは噴火とともに放出されたり、火山によっては噴火のない時でも恒常的にガスが放出していることもあります。火山ガスは無色で目に見えず、窪地に滞留していたガスに気がつかず、死亡するケースがあります。
火山ガスが放出されている火山には極力近づかないようにすると共に、やむを得ず近郊にいく場合は必ず火山ガス用のマスクを携帯しましょう。
トイレの対策
火山灰は岩石からできているため、水に濡れたり冷えると固まります。そのため、大量の火山灰が上下水道に入り込むと、一時的にトイレが使えなくなる懸念があります。非常用トイレを用意し、上下水道の回復まで待つ備えをしましょう。
トイレは1人当たり1日5回の使用を目安として、必要な回数分を用意します。期間は最低3日分、できれば1週間分を用意しましょう。
トイレの必要量の計算
トイレの使用回数目安=1人1日5回
- 家族3人を3日分=3人 × 3日 × 5回 = 45回分
- 家族4人を7日分=4人 × 7日 × 5回 = 140回分
- 家族5人を7日分=5人 × 14日 × 5回 = 350回分
非常用トイレは噴火以外の災害(地震等)や流通のストップ時、避難時、車の大渋滞時、アウトドア等でも使えるため、多めに用意していても損はしません。
食料品・飲料水の確保
全ての災害対策に当てはまる食料品・飲料水の備蓄は、噴火対策でも同様です。
まず、溶岩や火砕流からの避難時に、非常食・非常水の携帯は必須です。また、火山灰の大量降下にともない、飛行機の停止、高速道路の封鎖と一般道の速度制限、新幹線の停止と在来線の速度制限で、流通が大きく滞ることが予想されます。さらに、農作物への火山灰降下は植物の発育や収穫に影響を与えるため、噴火発生からしばらくたった後に、深刻な野菜不足が起きる可能性があります。また、火山灰には火山ガスが付着しているため、農作物や飲料用の貯水に降りかかった場合の健康への影響も懸念されています。
このような事態に備え、常に食料品・飲料水の備蓄に努めましょう。備蓄量は最低3日分が目安ですが、2週間分程度はあったほうが精神的な余裕が生まれるでしょう。通常の食事代わりにできる非常食・非常水であれば、余っても捨てずに活用できるため、多めの備蓄がお勧めです。
また、最近はローリングストックと呼ばれる食料備蓄方法が推奨されています。日常的に飲食するものを多めに買い、古いものから使って常に一定量がストックされているようにする方法です。避難時の食料持ち出しには向きませんが、自宅で一定期間の食料対策が必要な場合は推薦できる方法です。
その他生活用品の対策
火山灰の大量降下時にはあらゆる流通の滞りが予想されます。日常的に使っている用品で、無いと困るものは、多めにストックしておくようにしましょう。例えば、乳児用品、介護用品、医療用品、常備薬などです。
電気等エネルギーの対策
大規模な噴火による噴出物で、電気、ガス、水道などのインフラが一時的に使用できなくなる可能性があります。溶岩や火砕流、山体崩壊による破壊、火山灰による電線の断線などのほか、コンピュータ制御されているインフラに火山灰が入り込むことでショートする可能性も考えられます。また、太陽光パネルは自然災害に弱く、火山灰が積もると発電量が落ちます。
インフラ系統は最優先で復旧作業が行われます。壊滅的被害でない限り、数日持ちこたえていれば復旧する可能性が高いです。とは言え、その間の代替エネルギーは必要です。最低3日分、できれば1週間分用意しておきましょう。
代表的な対策品は、発電機、非常用ライト、ろうそく、ガスコンロです。
情報収集の対策
災害時にはリアルタイムの情報収集が欠かせません。ラジオの他、気象庁やその他の公的発信もスマートフォンで受信できます。電気がなくても使えるラジオ、電池の備蓄、スマートフォンの充電対策をしておきましょう。
どれくらいの量を準備するか?
噴火発生期間の長さは様々です。1日や数日と短く終わることもあれば、1ヶ月、または数年と長く続くこともあります。そのため、必要な備蓄量を一概に言えないところもありますが、当店の考える目安として、以下を参考にして下さい。
・基本は他の災害対策と同じで、最低3日分は準備する。ストック可能なものは、できれば1週間分。
・非常食や非常水は、精神的な安心感のためにも可能な限り多めに持つ。日常の食材のローリングストック(常に多めに在庫を持ち、古い順に使っていくこと)がお勧めです。ただし、都市ガスが災害で停止した場合、工事が地中のため、復旧に2ヶ月近くかかる可能性があります。なるべくガスを使わないで調理できる食材を考慮しておきましょう。(噴火での都市ガス停止の可能性は少ないですが)
・マスクは2週間分あると安心。噴火発生時には店頭や流通からあっという間に在庫が無くなることを想定し、事前の備えがお勧め。
・ゴーグルは1個あれば、破損しない限り使用可能。
・電気は数日以内に復旧されることが想定されるため、蓄電や発電系は控えめで良い。
・水道が災害により停止した場合は地中工事のため復旧に時間がかかります。応急的復旧工事で、災害発生から約2週間で50%、約2ヶ月で95%までの回復が想定されています。ただ、噴火災害では地中への被害は多くないと思われます。心配な場合は、非常用水を大量に備蓄することは保管場所を考慮しても難しいため、浄水器を用意しておくと良いでしょう。
・トイレは1人1日5回を目安に計算します。下水道が災害にあった場合、下水処理場の被害規模の程度で、地域により大きく異なります。早い場所では約1ヶ月、遅い場所で3ヶ月かかったケースもあります。そのため、非常用トイレは多めに準備しておいたほうが安心でしょう。災害で使わない場合でも、アウトドアやドライブの長距離渋滞対策として使えます。
・その他の医療品や衛生用品、日用品は、可能なものはローリングストックで常に多めにあるようにしておきます。数日は外出できなかったり、物流の滞りが起こる可能性があるためです。
次ページ →噴火対策その3 建物、車、精密機器、農作物の対策