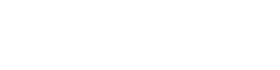噴火警報・噴火速報とは? ― 火山リスクを知り、備えるために

日本では、活発な火山活動による災害リスクを低減するために、気象庁が「噴火警報」および「噴火速報」という情報を発表しています。これらは「いつ」「どこで」「どの程度」の火山現象に警戒・対策が必要かを知るための重要な指標です。
ここでは分かりやすく「噴火警報/噴火速報」の違い、発表される条件、見方・使い方、そして私たちに求められる「備え」について解説します。
噴火警報とは?
「噴火警報(ふんかけいほう)」とは、火山の噴火に伴って 生命に危険を及ぼす火山現象(例えば大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流など)が発生するおそれがあると判断された場合に発表される “予報的な警報” です。
この警報には、「警戒が必要な範囲(例:火口周辺、居住地域、海域など)」が明示され、レベルによって登山を禁止する、避難を呼びかけるなどの対応が取られます。
警報の分類とその意味
警報は以下のように分類されます:
- 噴火警報(火口周辺):警戒範囲が火口周辺に限られる場合。例:山頂近く、火口周囲など。
- 噴火警報(居住地域):警戒範囲が居住地域まで及ぶ場合。すなわち、住民が被害を受ける可能性がある場合。
- 噴火警報(周辺海域):海底火山やその影響が海域に及ぶケース。
なぜこの警報が重要か?
火山活動が活発化している時、異常が観測されても「いつ噴火するか」「どこに被害が出るか」は正確には予測できないことが多いため、警報として「リスクがおおきい」状態を事前に伝える役割があります。
警報が発表された地域では、自治体・登山関係機関・住民が迅速に対応をとることが定められており、入山規制や避難などが現実化します。
噴火速報とは?
一方、「噴火速報(ふんかそくほう)」は、既に 噴火が発生した事実 を できるだけ速やか に伝える情報です。
登山者、火山近隣住民など、火山周辺にいる人々に対し「今動けるうちに安全な行動をとってください」という意味合いが強くなります。
速報が発表される典型的なケース
- 常時観測火山(監視体制のある火山)で、噴火警報が発表されていない段階で噴火が確認された場合。
- 噴火警報が既に出ている火山で、さらに噴火規模が大きくなった、または警戒範囲の拡大を検討する必要がある状況になったと判断された場合。
- 社会的影響が大きく、迅速に事実を伝える必要があると気象庁が判断した場合。
速報時に知るべきこと
- 発表される情報は簡潔で、主に「火山名」「発生時刻」「噴火があったという事実」など。
- 「噴火警報」と異なり、予兆段階ではなく 発生後の通知 なので、対象者(登山者、周辺住民)はすぐ行動を開始する必要があります。
- 速報が出た=「状況が進行中または重大である可能性がある」という意味を持つため、油断はできません。
噴火警報・噴火速報をどう読み取るか?
噴火警報・噴火速報をどのように読み取るべきでしょうか。知っておくべきポイントを整理します。
1、公式の発表を受け取る、確認する
- 気象庁公式サイト:火山ハザードマップ・火山活動状況・警報・速報などを掲載。
- テレビ・ラジオ・スマートフォンの防災アプリ・自治体メール配信など。
- SNSの一般投稿で情報が得られる場合もありますが、誤情報もあるため、「公式情報で確認」を推奨します。
2、警戒のレベル感を把握する
例えば、噴火警戒レベル(レベル1〜5)という指標が運用されており、レベルが上がるほど警戒すべき範囲・対応が拡大します。
速報が出た時点では、火山活動が急変した可能性があるため、「すぐに避難できる準備」が必要です。
※噴火警戒レベルについて詳しく解説
https://hun-ka.com/blogs/contents/volcanicalertlevels
3、火山や被害想定地域との距離から行動を検討する
- 登山中/火山近くを移動中:特に速報が出たら“滞在中止・速やかな下山・避難”を検討。
- 火山近隣住民・旅行者:警報が出ていない状態でも、異常音・地鳴り・煙・振動などを感じたら、速報を待たずして安全行動をとることが“先手の備え”です。
- 遠隔地域・観光目的の訪問者:警報・速報情報を事前にチェックし、「登る/近づく」判断を慎重に。また、飛行機や新幹線などの運行情報に注意しましょう。
登山・火山近隣に居住・観光や出張ごとの対応
噴火警報が発令された場合、登山中、火山近隣へ居住、観光や出張で遠方へ移動中の状況ごとに取るべき行動を解説します。
1、登山・山岳観光前にチェック:
- 目的の山(火山)が「常時観測対象火山」「噴火警戒レベル運用火山」かどうかを確認。→気象庁火山登山者向け情報提供
- 直近の火山活動状況・警報・速報の発表状況を気象庁や自治体サイトで確認。
- 登山ルート・退避ルート・避難場所を事前にマップ・記憶しておく。
- 天候悪化・地震・地鳴り・煙・異臭など「異常感」に気づいたら、予定を即座に撤回する判断を頭に置いておく。
2、火山近隣に居住・滞在する場合:
- 自宅や滞在先の「避難所」「避難ルート」をあらかじめ把握。
- 火山灰対策(窓閉め・マスク・ゴーグル)や情報収集手段(防災アプリ・自治体メール)を準備。
- 噴火警報が出たら、速やかに行政の指示に従い、安全な地域へ移動する準備を。
3、旅行者・出張者向けの注意:
- 旅行先が火山地帯であれば、旅行前に「噴火警報情報」を確認。旅行保険で「噴火・火山灰被害」が補償対象かどうかもチェック。
- 火山活動が活発な期間(警戒レベルが高め/入山禁止近く)には、観光ルートを変更する柔軟性を持っておく。
- 登山・火口近く見学を予定している場合、安全確保できるガイド付きツアーを選ぶのも安心材料。
- 噴火発生時には飛行機や新幹線の停止、高速道路の封鎖、一般道の交通制限などが起きるので、利用予定の交通手段の状況を確認しておく
噴火警報・噴火速報の発表を受け取る・確認するには
噴火警報・噴火速報は、気象庁HP、テレビやラジオ、スマホアプリなど事業者が提供するサービスで知ることができます。
気象庁 噴火警報・噴火速報
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.5/137/&contents=volcano
事業者が提供するサービス(気象庁HP)
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/
気象庁 ソーシャルメディア
警報の発信サービスではありませんが、公式な情報源として、気象庁の運営するソーシャルメディアをご活用ください。
気象庁防災情報 X
https://twitter.com/JMA_bousa
気象庁ソーシャルメディアアカウントの一覧
https://www.jma.go.jp/jma/menu/social_info.html#list