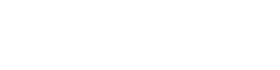噴火対策その6 噴火が起きたときにすぐ取る行動、取ってはいけない行動
噴火が起きたらどうする?
急に噴火が起きたら? すぐに取るべき行動をまとめました。
1、噴火に関する情報を収集する。
噴火のニュースや噂を聞いたら、まずはデマでないか真偽の確認と、噴火の規模について調べるために、気象庁などの公的な発表を確認します。
気象庁 災害情報
噴火発生の確認が取れたら、お住まいの場所や現在の場所に、どの程度影響するか、発表内容を確認します。
ただし、状況によっては、調査に時間をかけすぎると次の行動を取る前に交通網が止まったりするので、移動しながら調べるなど臨機応変に対応しましょう。
2、移動の判断:避難か? 帰宅か? 待機か?
・避難指示(噴火警戒レベル5)の出ている場所なら、行政の指示に従い、一刻も早く避難します。家族や自身が外出している場合は、すぐに連絡を取り合いましょう。
・避難するほどではないけれど火山灰降下が予想される範囲内にある場合、噴火後まもなく、火山灰の影響のあるエリアの飛行機、新幹線の運行停止と、高速道路の封鎖、在来線や一般道路の規制が始まります。勤務や用事で外出しているなら、可能な限り早く帰宅のために移動しましょう。例えば東京出張中に富士山が大きめの噴火をした場合、4時間ほどで火山灰が都内へ到達すると予想されます。その場合は噴火発生から1〜2時間が勝負となります。新幹線や高速道路など、停止される前に移動しましょう。どうしてもすぐの帰宅が難しい場合、ホテル等の宿泊場所を早めに押さえましょう。
・幸いにも自宅にいる場合、避難の必要がない地域であれば、無理な外出はせずに待機しておきましょう。外出している家族がいる場合は、連絡を取って状況を確認しておきます。
3、食糧や物資の確保
帰宅などの移動に時間がかかる場合や、オフィスやホテルでの泊まり込みになる場合、なるべく早めにスーパーやコンビニ等で飲料水や食べ物を確保しましょう。必要な方は衛生用品等も買っておきます。ただし、他の人も同じく困難な状況にあるため、限度を超えた確保をせず、譲り合いの精神で互いに助け合いましょう。
自宅には最低3日分の食事や飲料水を確保しましょう。スーパーや各店舗はあっという間に売り切れる可能性があるため、当日は早めの購入をお勧めしたいところですが、理想的にはあらかじめ防災備蓄をしておくことです。自身は備蓄分で対応し、噴火発生当日の店舗購入は他の人に譲るくらいの余裕が望ましいです。
噴火発生後にすぐ取る行動としては以上です。移動や宿泊、食料品を確保した後は、出どころの確かなニュースを確認しつつ、公共の安全や秩序を守りつつ、無理のない行動をとりましょう。
やってはいけないこと
反対に、噴火発生時にやってはいけない行動をまとめます。
1、出どころの怪しい情報(デマ)を鵜呑みにする
災害時に必ずと言ってよいほど出てくるのが、極端な内容で煽るデマ情報です。災害時の有名なデマの事例としては、1923年の関東大震災では「朝鮮人3000人が襲って来る」、2011年の東日本大震災では「原子力発電所が爆発して放射能の混じった死の雨が降りつつある」、2016年の熊本地震では「近くの動物園からライオンが放たれた」などです。こうしたデマは確信犯的に嘘を流された情報もあれば、聞きかじった情報を精査せず親切のつもりから拡散されたものもあります。災害では、災害自身の被害よりも、人々のパニックや誤った行動からの被害が大きいとも言われています。最近ではディープフェイクによる本物と見まごう映像や画像も作れるため、ますますの混乱が予想されます。少しだけ冷静になり、情報の出どころ、信頼性を確認する余裕を持ちましょう。
2、デマの発信側になる
上記と反対に、デマの発信側になることです。確信犯として嘘を流すのは言語道断ですが、注意するべきは根拠のない情報をあわてて他の人へ広めてしまうことです。パニックはパニックを呼びます。自然災害であれば気象庁や公的な発表を共有するにとどめ、それ以外の情報は個人の自己責任で取捨選択する範囲にとどめておきましょう。
最近では、「災害の発生した地域で物資が不足し、支援を要請している」として役場や避難所の連絡先を記載した、人の善意を利用した偽情報の拡散も出ています。偽情報でも支援が届けば有難いのでは、と思いがちですが、現地では必要のない物資の整理や場所の確保、廃棄、問い合わせ対応などで、災害対応の貴重な人的・時間的・空間的リソースが裂かれます。善意に基づく発信であっても、情報は発信元と真偽を確認するステップを踏みましょう。
3、車や自転車での無理な移動
噴火発生時の避難や移動はすぐにおこなった方が良いのですが、注意点もあります。場所やタイミングによっては、車での移動は渋滞を引き起こしたり、事故や故障の多発で道路上で動けなくなることがあります。道路で事故が発生した場合、緊急車両が通れないなど、大きな迷惑をかけます。例えば富士山火山防災対策協議会は2023年3月に、噴火の予兆や発生時の避難を、従来の車での避難から、原則「徒歩避難」に改めました。渋滞を混乱を避けるためとしています。車での移動が渋滞や事故を引き起こす可能性がある場合、車を安全で邪魔にならない場所に止めて、徒歩や公共交通機関を使った移動を検討しましょう。
また、火山灰が降っている時には、車や自転車の移動は注意して下さい。タイヤがスリップします。噴火の収まった時でも、地面に薄くでも火山灰があればタイヤが滑りますので、無理な運転をせず十分な注意を払ってください。
4、コンタクトレンズをつけたままにする
火山灰が目に入ると網膜を傷つけます。コンタクトレンズをつけていても同様です。コンタクトレンズを着けていた場合、火山灰が降り始める前に外し、眼鏡に切り替えましょう。